改善の誤解から抜け出す第一歩
「改善」という言葉を聞くと、多くの経営者が「悪いものを直す」や「ミスを減らす」といったイメージを持ちがちです。
確かに、それも改善の一部ではあります。
しかし、本質はそこではありません。
改善は単なる修正作業ではなく、「未来を描くための第一歩」です。
つまり、会社の売上を伸ばし、組織を持続的に成長させるための仕組みづくりなのです。
改善には2つの売上アップの視点がある
改善を“未来のための投資”として捉えると、売上に直結する2つの視点が見えてきます。
- 営業の行動量を増やす仕組みづくり
DXを取り入れることで業務の効率化が進み、営業マンが書類や確認に追われる時間を削減できます。
浮いた時間を顧客対応や新規開拓に振り向けることで、売上アップに直結します。 - 作業工数を減らして利益率を上げる仕組みづくり
従来の手作業や重複作業をDXで効率化すれば、1つの仕事にかかる工数が減り、コスト削減につながります。
余った人や時間を新しい案件や改善活動に振り分けられるため、自然と利益率が高まります。
改善は“経費削減”だけでなく、“売上を伸ばす原動力”でもあることを理解する必要があります。
現場が動かない原因は「ビジョン不在」
ではなぜ、多くの改善活動が続かないのでしょうか。
理由はシンプルで、現場に「なぜこの改善をするのか」というビジョンが届いていないからです。
例えば「機械の稼働率を上げろ」と指示しても、社員には「なぜそれが必要なのか」が見えない。
「作業効率を上げろ」と言っても、目の前の仕事に追われる現場には響きません。
改善を進める前に、経営者自身が描く未来像を「現場に伝わる言葉」に変えること。
ここが整っていなければ、どんな施策も長続きせず、形骸化してしまいます。
改善は“問題解決”ではなく“源流づくり”
多くの会社が「問題が出たから改善する」というスタンスで動いています。
もちろん、問題解決は大切です。
ですが、本当に必要なのは「問題が起きる前に整える」こと。
経営者が描く未来像を源流に据え、そのビジョンを現場で動く計画に落とし込む。
これこそが、現場が動き続ける改善の土台になります。
つまり、改善は「不具合対応の延長線」ではなく、「未来に向かう源流づくり」なのです。
ビジョンが現場を変える具体例
ある製造業の企業では、長年「機械を止めるな」という指示ばかりが現場に飛んでいました。
確かに稼働率は高まりましたが、社員は疲弊し、品質トラブルも増加。
そこで経営者が改めてビジョンを言語化しました。
「私たちは“安心して使える製品”を地域に届けたい」
この言葉を軸に改善活動を整えると、現場の意識は大きく変わりました。
単なる稼働率ではなく、品質安定や工程の見える化に注力するようになり、結果的に売上も伸びたのです。
ビジョンは現場の心を動かす力を持っています。
整え屋の役割は“橋渡し”
私の役割は、経営者の理念や未来像を「現場で動く改善計画」に翻訳することです。
抽象的な言葉を具体的な行動に変え、数字で測れる形に落とし込む。
経営者が描く未来と、現場が実際に動ける仕組み。
この2つをつなぐのが「整える」という仕事であり、改善活動を長続きさせる秘訣です。
改善は“現場を動かすビジョンづくり”から
改善は悪いことを直すものではなく、未来を整えるための仕組みづくりです。
そして、そのスタート地点は「ビジョン」です。
経営者の想いを言葉にし、数字に結びつけ、現場に届く形に変える。
これができたとき、社員は自分の役割を理解し、改善活動は自然に回り出します。
📩 現場を動かすビジョンを一緒につくりませんか?
「理念はあるが、現場に伝わらない」
「数字は追っているが、社員が動かない」
そんな課題を感じている経営者の方。
まずは“源流づくり”としてのビジョン整備から始めましょう。
私は、社長の未来像を“現場で動く計画”に変えるお手伝いをしています。
ぜひ一度、ご相談ください。
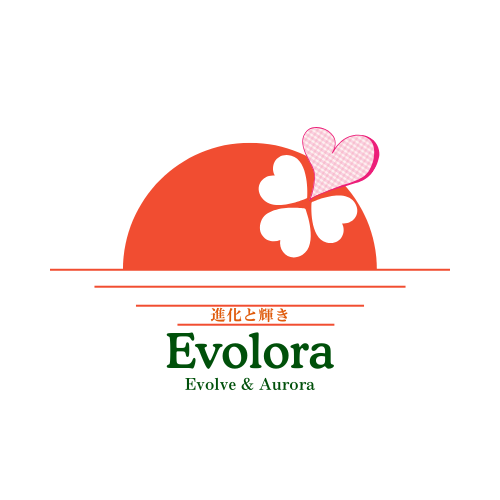 技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー
技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー 


