誤解されがちな「改善」のイメージ
「改善」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?
多くの経営者の方が「悪いところを直す」「ミスや不具合を減らす」という発想で捉えています。
もちろん、それも大切な一面です。
しかし、それだけに留めてしまうと、改善は“守りの活動”になってしまい、売上を伸ばす力にはつながりません。
改善とは本来、未来の売上をつくるための攻めの技術です。
改善を「売上を生む技術」と再定義すると、具体的には次の2つの方向性があります。
1. 効率化で営業や現場の行動量を増やす
DXを取り入れることで、これまで人が時間を割いていた作業を自動化できます。
たとえば営業マンが資料探しや入力業務から解放されれば、その分、訪問件数や提案の準備に時間を割けます。
「行動量」が増えれば、売上のチャンスも自然と拡大します。
これは効率化を“攻め”に転換する代表例です。
2. 工数削減で利益を守り、再投資へ回す
もう一つの視点は、コスト構造の見直しです。
手作業や紙中心の運用では、必ず余計な工数や待ち時間が発生します。
この無駄を削減し、1つの作業あたりのコストを下げれば、その分の時間や資金を別の付加価値業務に回せます。
つまり「守り」ながら「攻める」仕組みを同時につくるのです。
製造業では「機械の稼働率を上げれば売上が伸びる」と考えられがちです。
しかし、在庫が増えすぎれば資金繰りを圧迫しますし、現場の負担も増えます。
本当に注目すべきは「稼働率」ではなく、行動率と改善率です。
社員がどれだけ付加価値を生む活動に時間を割いているか。
改善がどれだけ“売上を生む仕組み”に反映されているか。
この視点が抜けていると、どれだけ動いても利益が積み上がりません。
改善が「売上を生む技術」として根づいている会社には共通点があります。
- 改善提案が「コスト削減」だけでなく「売上向上」につながっている
- 経営者のこだわりよりも「現場で成果が出るか」を判断基準にしている
- DXやツール導入が「補助金ありき」ではなく「戦略の一部」となっている
- 余剰工数を新しい挑戦や顧客対応に再配分できている
つまり、改善そのものを「未来への投資」と捉えているのです。
改善を「悪を直す」ものと考えているうちは、会社は守りに入ります。
ですが、改善を「売上を生む技術」と再定義すれば、現場の動きが変わり、経営判断も変わります。
そしてこれは、特別な才能や大きな投資がなくても始められる取り組みです。
重要なのは、目的をズラさないこと。
「改善の目的は、売上を伸ばし、利益を積み上げ、未来を描くこと」
この一点を共有するだけで、社員のモチベーションや行動は確実に変わっていきます。
私は現場に入り込み、経営者の想いと社員の動きをつなぐ「伴走型コンサル」として活動しています。
単なるアドバイスではなく、実際に仕組みをつくり、改善を“利益の仕組み”に落とし込むのが私の役割です。
もし今、
「改善はやっているけど成果につながっていない」
「稼働率を上げても利益が伸びない」
と感じているのであれば、それは目的がズレているサインかもしれません。
📩 御社に合った“売上を生む改善”の第一歩を一緒に考えてみませんか?
まずはお気軽にご相談ください。
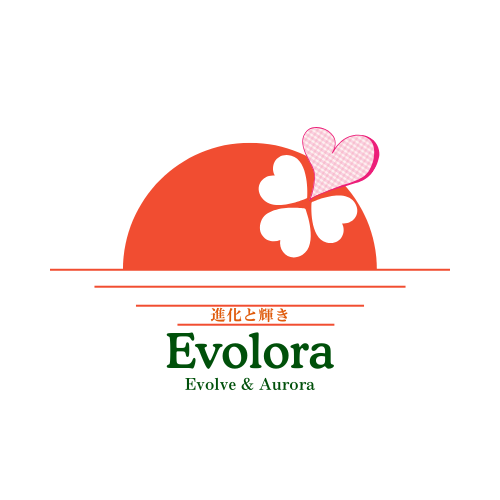 技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー
技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー 


