〜“作っただけ”をやめて、“使われる仕組み”を育てる〜
「ベテランのノウハウをマニュアルにしました」
「技術伝承のために、ドキュメントを整えました」
「教育資料、動画化までしています」
それなのに――
「なぜか現場で使われていない」
「結局、属人化が解消しない」
「改善につながらない」
この原因は、たったひとつ。
“仕組みとして運用されていないから”です。
ノウハウを形式知化することは目的ではありません。
それはあくまで、「現場で使われて成果を出す仕組み」への第一歩です。
形式知化という言葉を聞くと、多くの現場ではまず「マニュアルを作る」が浮かびます。
確かに、暗黙知を言葉にすることは必要です。
でも、それだけでは現場は変わりません。
事例:誰も見ない50ページのマニュアル
ある製造現場で、ベテランの知見をまとめた立派なPDFマニュアルを作成。
写真や図解も多く、上層部からの評価も上々でした。
しかし数ヶ月後、後任者に聞くと――
「分厚すぎて見る時間がない」
「今どこに保存されてるか分からない」
「現場ではスマホで見られない」
つまり、「形式知化」はしたけれど、現場で運用できていない=死んだ資料になっていたのです。
形式知は、“使われてこそ価値がある”。
それを継続的に「使われる仕組み」に乗せることが、本当のゴールです。
1. 「見つけやすい」「使いやすい」導線設計
- タブレットやスマホで見やすいUI
- CanvaやNotionで1ページ完結型に
- 目的ごとにリンクが整理されたナレッジポータル
現場で「3秒でアクセスできる」状態が、“使われる前提”の基本です。
2. 教える側・使う側の“温度差”をなくす
- ベテランが“作って満足”になっていないか?
- 若手が“質問しづらい雰囲気”になっていないか?
- マネジメントが“整備したつもり”になっていないか?
現場とマネジメントの距離感を埋めるのも、仕組みの役割です。
3. “更新され続ける”運用設計
資料は「完成」した瞬間から古くなります。
だからこそ、
- 月に1回、更新フラグが立つチェックシステム
- 誰でも追記・修正できるオープンなフォーマット
- ChatGPTを活用した自動要約や再構成の仕組み
こうした**“育てる仕組み”がなければ、形式知は劣化していきます。**
Evoloraのコンサルティングでは、単なるマニュアル作成では終わりません。
現場に入り込み、“使われる・回る・育つ”までを一緒に伴走します。
ステップ1|現場の声を聞きながら棚卸し
- どの工程が属人化しているか?
- どの情報が“言葉になっていない”か?
- どこに“判断の迷い”があるか?
これをヒアリングと現場観察で見える化していきます。
ステップ2|“見る人のため”の形式知化
- ChatGPTで会話形式のQ&Aを生成
- Canvaで工程図+注意ポイントを1枚にまとめる
- 動画+音声でベテランの解説を記録
誰かの「つまずきポイント」が消えるような設計を一緒に考えます。
ステップ3|“運用する仕組み”まで構築
- ナレッジ更新を誰でも行える文化の育成
- LINEで簡単に問い合わせできる仕組み
- AIとの連携で「探さなくても答えが届く」仕組み
形式知を、現場に馴染む形で循環させるのがゴールです。
「でも、それって時間もコストもかかりませんか?」
確かに、最初の設計は少し手間がかかります。
でも、それを怠った結果、
ベテランが休めない・新人が育たない・改善が止まる――
この“ムダなコスト”のほうが、よほど大きいのです。
「作ったのに、誰も見ていない」
「整えたのに、活用されていない」
「マニュアルがあっても、失敗が減らない」
これは、資料の問題ではありません。
“仕組み”の問題です。
だからこそ、形式知化には「運用される仕組み」が不可欠。
仕組みで使われ、継続され、改善されていく。
それこそが、技術を資産に変える唯一の方法です。
- 「形式知化が続かない」
- 「マニュアルが使われない」
- 「現場で仕組みが定着しない」
Evoloraでは、**一緒に作り、一緒に回し、一緒に改善する“伴走型支援”**を提供しています。
AI、動画、Canvaなどのツールを活用しながら、
御社に合った“使われる形式知化”の仕組みづくりをお手伝いします。
まずは、今お困りのことをお聞かせください。
👉【お問い合わせはこちら】
https://evolora.net/contact/
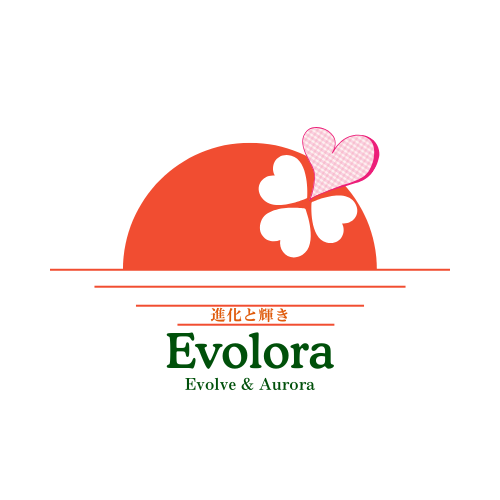 技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー
技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー 


