制度が機能しない理由は“根っこ”にある
「そろそろ評価制度を導入したい」
「社員の頑張りを見える化して、やる気につなげたい」
多くの経営者がこう考え、評価制度や人事制度の整備に着手します。
しかし、実際に制度を導入しても「不公平だ」「形だけだ」という声が出て、期待したほど成果が出ないケースも少なくありません。
その原因は、仕組みそのものではなく、制度を支える“根っこ”が言語化されていないことにあります。
つまり、**評価制度の前に必要なのは「社長の想いを言葉にすること」**なのです。
改善は仕組みではなく「未来を叶える道具」
経営における改善とは、「悪い部分を直すこと」ではなく「未来を叶えるための手段」です。
評価制度も同じ。
「制度を整える」ことが目的ではなく、社員一人ひとりが未来に向かって力を発揮できる環境をつくることが目的です。
ですが、経営者の想いが言語化されていないまま制度をつくると、社員にとっては「数字を追いかける枠組み」にしか映りません。
これでは形骸化し、改善の力が削がれてしまいます。
経営者の想いを“現場に届く言葉”にする
では、想いを言語化するとは具体的に何でしょうか?
それは、経営者の中にある漠然とした「こうありたい」を、社員にとっての「行動基準」や「判断の軸」に落とし込むことです。
例えば、
- 「お客様第一」 → 「お客様の困りごとを聞き、24時間以内に対応する」
- 「挑戦する組織」 → 「小さくても新しい試みを月に1回は提案する」
このように、想いが行動に変換されると、現場の社員は迷わず動けるようになります。
そして、それが評価制度や仕組みに反映されると、初めて制度が“血の通った仕組み”として機能し始めるのです。
DXも制度も「想い」がなければ形骸化する
最近ではDX化やAI導入の波もあり、「制度+デジタル」で改善を進めようとする企業が増えています。
しかし、ここでも同じ落とし穴があります。
システムやツールはあくまで手段にすぎません。
「何のために導入するのか」が曖昧なまま進めると、社員は「また新しいツールが来た」と受け身になり、活用が定着しません。
逆に、経営者の想いが言語化されていれば――
「このDXは、現場の時間を削減して、お客様対応にもっと力を注ぐためにある」
「この仕組みは、みんなの挑戦を公平に評価するためにある」
と、社員は制度やDXを自分ごととして受け止められるのです。
想いの言語化が“売上を生む改善”に変わる
想いを言語化すると、改善は次の2つのルートで売上に直結します。
- 余力を生み出す改善
社員が目的を理解すれば、日常のムダを自ら削減する行動が生まれます。
ルーティン業務が効率化され、余った時間を新しい活動に回せます。 - 行動を加速する改善
経営者の想いが現場で共有されれば、営業や製造現場の行動率が上がります。
その結果、顧客接点が増え、売上が自然に伸びていきます。
つまり、評価制度やDXは「想いを実現するための道具」に過ぎず、本当の起点は経営者の言葉なのです。
制度は“根っこ”があってこそ活きる
評価制度やDXの導入を検討する前に、まずやるべきことは一つ。
経営者の想いを現場に届く言葉にすること。
それがあるからこそ制度が機能し、改善が“未来を叶える仕組み”へと変わります。
経営者の想いを言語化し、現場に届くように設計していく――
そのプロセスを丁寧に進めることで、売上も人材も同時に伸びていくのです。
📩 「自分の想いを、現場に届く言葉にしたい」と思われた経営者の方へ
制度やDXに投資する前に、まずは一緒に“想いの翻訳作業”から始めてみませんか?
私が現場に入り、伴走しながら仕組みに落とし込むお手伝いをいたします。
お気軽にご相談ください。
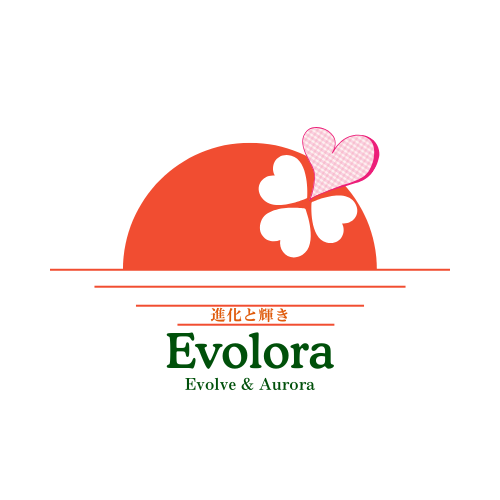 技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー
技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー 

