経営者の想いと現場の現実のズレ
経営者として「もっと会社を良くしたい」「社員の働き方を楽にしたい」と思い描く未来。
しかし、その想いが現場にうまく届いていないと感じたことはありませんか?
会議では頷いてくれるのに、現場の行動が変わらない。
改革のために投資したシステムが、結局使いこなされない。
社員に「どう思っている?」と尋ねても、「特に問題ありません」と返ってくる。
その裏側には、経営と現場の間に横たわる“見えない壁”が存在します。
この壁に気づかずに改善を進めると、成果は一時的で終わり、本当に実現したい未来には届きません。
改善は「悪いものを直す」ではなく「未来を叶える」ためにある
多くの企業で、改善という言葉は「無駄を削減する」「コストを減らす」といった“守り”の意味で使われています。
しかし、本来の改善は、未来の売上を生み出す“攻めの技術”です。
改善には大きく二つの道があります。
- DXで効率化し、余力を売上活動に回す
定常業務を効率化して、社員が持つ時間と労力を「お客様に向き合う活動」や「新しい挑戦」に振り向けられるようにする。 - 営業や現場の行動量を増やし、成果を拡大する
データを活用して行動を可視化すれば、社員は「どこに力を注げば結果が出るか」がわかり、行動の質と量が変わる。
つまり改善とは、「経営者が思い描く未来」を現場に接続するための架け橋なのです。
「伝わらない」のは、想いが弱いからではない
経営者の想いが届かない理由は、決して熱量やビジョン不足ではありません。
むしろ、多くの経営者は誰よりも会社の未来を考えています。
問題は、その想いを現場の「日常の行動」にまで落とし込めていないこと。
- システムを導入しても、社員にとって「なぜ必要か」が見えない
- 改善の目的が「コスト削減」としか伝わっていない
- ビジョンは語られても、現場にとっての「今日の一歩」が示されない
このように、想いが仕組みに変換されないまま現場に渡されているのです。
想いを「仕組み」に変えると現場は動く
現場が動くためには、経営者の言葉を「計画」と「仕組み」に変える必要があります。
たとえば――
- 曖昧な「効率化」ではなく、「月に10時間を削減して新規顧客への訪問に充てる」という形にする
- 「改善しよう」ではなく、「来月までに手作業の帳票をデジタル化する」という具体的なゴールにする
- さらにその進捗を、経営層と現場が一緒に見える化する
このように“未来の姿”が“現場で動く計画”に変わったとき、経営者の想いは初めて社員に届きます。
そして改善は単なる「節約」から「未来を実現する戦略」へと進化するのです。
経営者と現場をつなぐ伴走型アプローチ
私はこれまで、製造業やサービス業の現場で数多くの改善を支援してきました。
その経験から強く感じるのは、改善は「言う」だけでは動かないということです。
経営者の想いを聞き取り、それを「現場で動く仕組み」に翻訳し、社員と一緒に試行錯誤しながら回していく。
この伴走のプロセスこそが、改善を“机上の空論”から“現実の成果”へと変えるのです。
経営者が一人で背負う必要はありません。
想いを仕組みに変え、現場に浸透させるサポートは、外部の専門家だからこそ冷静かつ客観的に行えます。
想いを届けることで、未来が動き出す
改善は、悪い部分を直すためのものではありません。
経営者の想いを現場に届け、未来の売上を生むための第一歩です。
そのためには、想いを“現場で動く計画”に変換し、仕組みに落とし込むことが欠かせません。
それができたとき、社員は「やらされ感」から解放され、自ら未来を描く仲間へと変わっていきます。
📩 「経営の想いを現場に届けたい」と感じた方へ
改善は、一人ではなく伴走者と共に進めることで加速します。
ぜひ一度、貴社の現場に合わせた改善の進め方を一緒に考えてみませんか?
お気軽にご相談ください。
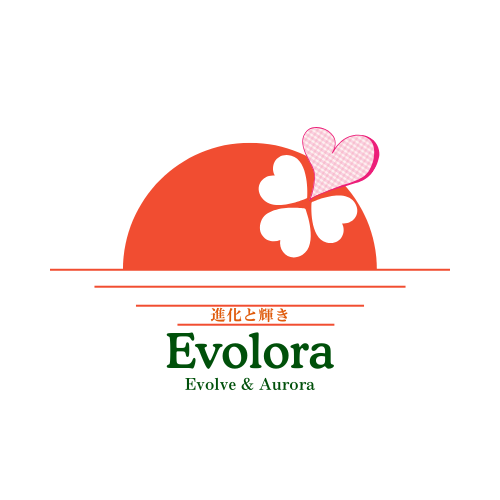 技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー
技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー 


