――声なき声が、前向きな改善の原動力になるとき
「どうせ言ってもムダ」
「結局、やるのは現場なんでしょ?」
「またトップが勝手に決めたよ」
DX推進や業務改善を進めたい経営者の多くが、
現場の“冷めた反応”に悩まれています。
でも、そうした反応は本当に“やる気がない”からでしょうか?
いいえ。
実はその多くが「言いたいことがあるのに、言えない」
もしくは「どうせ言っても変わらない」というあきらめの裏返しなのです。
不満があるということは、
そこに“問題を認識できる視点”があるということ。
それ自体は悪いことではありません。
問題は、それが提案や改善行動に変わらないまま、
愚痴や諦めに変換されてしまう構造です。
では、なぜそうなってしまうのか?
・現場の声を吸い上げる仕組みがない
・改善をしても、評価されない
・誰がどこまで提案していいかの線引きが曖昧
・会議はあるが“報告の場”で終わってしまう
・改善に使える時間や裁量が与えられていない
こうした背景が積み重なることで、
「言うだけムダ」が組織文化になってしまうのです。
だからこそ必要なのは、不満を“提案”に変える仕組みづくりです。
「声が上がらないから満足している」ではなく、
上がる構造がないから黙っているという視点を持つこと。
では、どんな仕組みが効果的でしょうか?
✔ 業務フローの可視化:誰が何をしているか、共有できる土台
✔ 属人化の排除:1人に依存しない業務設計で、余白を生む
✔ 改善アイデアの受付システム:日報やチャット、ふせんでもOK
✔ 小さな提案でもOKとする風土:否定されない経験が安心感に
✔ 評価と実行のサイクルをつくる:提案がカタチになる流れを体験する
こうした仕組みの整備が、
現場の空気を「ただの愚痴」から「建設的な提案」へと変えていきます。
「そういえば、こうした方が早いですよ」
「今のやり方、変えたらもっとラクになりそうです」
最初は控えめだった現場の声が、
いつの間にか前向きな提案に変わってくる。
それは、整った仕組みのなかで
「安心して発言してもいい」という心理的安全性が生まれた証拠です。
そして一度「自分の声が組織を動かす」経験をした社員は、
他人事だった改善活動を“自分ごと”として捉え始めます。
仕組みが整えば、人は変わります。
変えようとしなくても、変わるのです。
私は、単なるアドバイザーではありません。
実際に現場に入り、業務の見える化や仕組み作りを
**一緒に作業しながら整えていく“伴走型支援”**を行っています。
・「改善をしたいけど、どこから手をつけていいか分からない」
・「声の出ない組織を変えたい」
・「提案が生まれる文化を育てたい」
そんな想いをお持ちなら、
Evolora公式LINEまたはお問い合わせフォームより
「提案が生まれる仕組みをつくりたい」とご相談ください。
不満は、宝の山です。
仕組みで整えれば、会社の未来は大きく変わります。
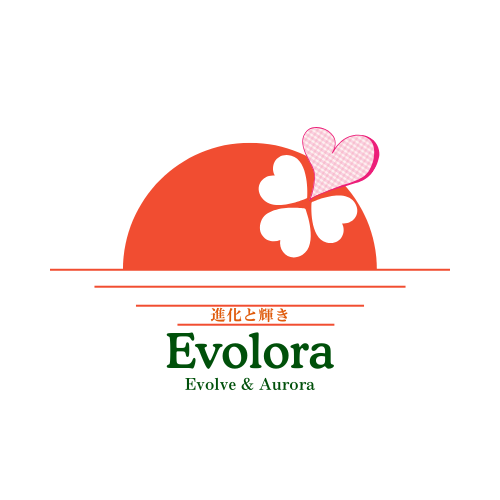 技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー
技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー 


