〜技術を“仕組み”として残すか、“記憶”とともに消すか〜
AIや自動化が進む今でも、製造業の現場には必ず人が関わる工程が残ります。
検査、組立、調整、判断――
“人だからこそ気づける”違和感や、“経験でしか分からない”判断の蓄積。
その一つひとつが、現場の品質と生産性を支えてきました。
でも、こうした技術やノウハウが、今、急速に失われつつあることをご存じでしょうか?
ある車載部品メーカーで、長年現場を支えてきたシルバー社員が退職しました。
彼は寸法検査のエキスパート。
測定器を使うのではなく、光の反射や微細なズレを“目で見て”判断する達人でした。
技術の標準化はされておらず、マニュアルも“感覚”に頼った口伝のみ。
後任に引き継がれることはなく、2ヶ月後には品質クレームが倍増。
こうして、何十年もかけて蓄積された“技術の財産”は、たった数週間で失われたのです。
多くの企業がこう言います。
「うちは属人化してるけど、○○さんが何とかしてくれている」
「教育や引き継ぎにかける時間がない」
「マニュアル化したいけど、何から始めればいいか分からない」
でも、それを後回しにした結果――
- 担当者が休めない
- 若手が育たない
- 現場が疲弊する
- 知見が失われる
経営リスクは、確実に蓄積されていきます。
なぜ“技術継承”が進まないのか?
- 「技術=経験=言語化できない」と思い込んでいる
- ドキュメントを作っても“使える仕組み”になっていない
- 誰かがやってくれるという“暗黙の期待”に依存している
でも今こそ、「人に依存しない、技術が残る仕組み」が必要です。
技術承継は、2つの層で行うことが重要です。
1. 全社で活用すべき技術・業務は標準化し、仕組みに落とす
- 作業手順をプロセスマップで整理
- ベテランの判断基準を図・写真・動画で記録
- CanvaやNotionで「誰でも見える」形にする
現場で誰がやっても同じ結果を出せるように、判断も含めて標準化していきます。
2. 事業のコアとなる技術は、深掘りして伝える
- なぜこの設計思想にしたのか?
- どんな失敗経験があり、どう乗り越えたのか?
- 顧客の信頼を勝ち取るために守ってきたことは何か?
これらは単なる手順ではなく、組織の「文化」として次世代に残すべきもの。
インタビュー、対話、動画記録を通して、背景ごと伝える仕掛けが必要です。
私たちは、“作って終わり”ではなく、
一緒に改善し、一緒に運用し、一緒に次世代へつなげるスタイルを取っています。
- ヒアリングで現場のノウハウを引き出す
- 見やすく、使いやすい形に整える(Canva・ChatGPT活用)
- 運用設計や教育のしくみ化までサポート
机上のコンサルではなく、現場と一体になって動きます。
「まだ○○さんがいるし、今すぐやらなくても…」
「人が足りなくて、それどころじゃない」
「うちみたいな中小企業では難しい」
そう思ってしまう気持ちも分かります。
でも、その“今じゃない”が続いた先には、
“残すべき技術が消えてしまった”という未来が待っています。
自動化が進んでも、人が関与する限り、技術は必ず発生します。
そしてその技術は、「誰かの経験」ではなく、「組織の資産」として残さなければならない。
人が介在する限り、技術継承は“選択肢”ではなく、“必須”です。
いま残さなければ、10年後に後悔しても、もう遅いかもしれません。
- 属人化の解消
- 技術・ノウハウの継承支援
- 動画・AI・Canvaを活用した見える化と教育設計
一緒に現場に入り、一緒に作業し、仕組みに落とし込みます。
まずは、今抱えている課題をお聞かせください。
👉【お問い合わせはこちら】
https://evolora.net/contact/
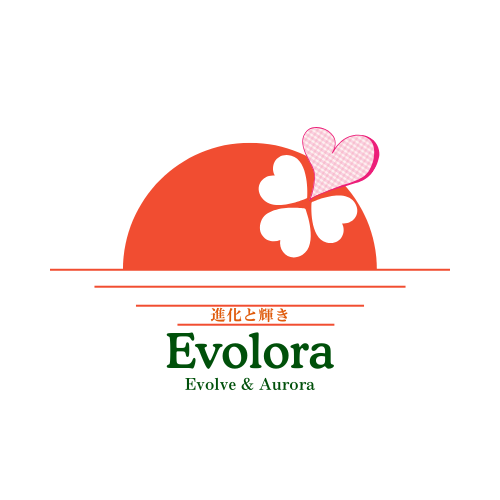 技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー
技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー 


