〜経験が消えるか、資産になるか〜
「○○さんの退職で現場が混乱した」
「手順は分かるけど、“あの人の判断”ができない」
「代替は育てているが、思うようにいかない」
今、多くの製造業が直面しているのは、技術継承の壁です。
長年現場を支えてきたベテラン技術者やシルバー人材の“知恵”や“経験”が、
形として残っていない――
それは、目に見えない資産の流出であり、
将来の競争力を左右する“経営課題”に他なりません。
ある車載部品工場では、
再雇用中のシルバー社員が担っていた「段取り替え作業」が、
後任にうまく引き継げず、ライン全体が数日停止しました。
原因は、口頭の伝承と場当たり的な指導。
「やりながら覚えて」と言われ続けた若手社員は、
“覚えきれない”プレッシャーに疲弊。
「手順は分かっても、勘どころが分からない」と戸惑う毎日。
そして数年後、若手は転職し、技術も残らず。
失われたのは人だけではなく、“技術そのもの”だったのです。
技術継承が進まない背景には、
属人化と“目に見えない知識”の存在があります。
1. 「言葉にしにくい経験」は放置されやすい
- 手順にない調整
- 感覚で判断している異常検知
- 失敗を回避する“ちょっとした工夫”
こうした「暗黙知」は、記録が難しく、後回しにされがち。
でも、実はここにこそ、“競争力の源泉”が隠れています。
2. 引き継ぎの負担が個人に偏っている
教える時間がない。
記録する余裕がない。
そんな中で「○○さんに聞いて」と頼る構造が生まれます。
結果的に、ノウハウが1人に集中=属人化が進行。
引き継ぎが「イベント」ではなく、「日常」で行える仕組みが必要です。
3. マネジメントと現場の認識ギャップ
- 経営:「AIや自動化で効率化を進めたい」
- 現場:「そんな時間も余裕もない」
この温度差により、改善や継承に向けた行動が止まってしまう。
技術を“資産”として捉える意識が、全社で共有されていないことが、
最大の壁になっています。
では、今の技術を“残る資産”に変えるにはどうすればいいのでしょうか?
答えは、記録・仕組み・文化の3段階です。
ステップ1:話してもらう・聞き出す
技術は、話すことで初めて明文化できます。
- 「どうやって判断しているのか」
- 「失敗しないために意識していることは?」
- 「やってはいけない例は?」
これを動画・音声・テキストなどでまず記録。
AIを使えば、対話を自動で文章化し、ポイント抽出まで可能です。
ステップ2:誰でも再現できるよう整える
収集した知識を、現場で使いやすい形に整えます。
- Canvaで簡易マニュアル化
- ChatGPTでFAQ生成
- 動画をスマホで確認できるように保存
現場が“使いやすい”形こそが、定着のカギです。
ステップ3:「継承する文化」を根づかせる
- 新人が“教えてもらう”のではなく、“記録から学べる”仕組み
- ベテランの「判断」や「考え方」を共有する社内勉強会
- 改善や工夫を更新していくナレッジベース
“記録して残す”ことが当たり前になる文化が、組織の競争力を底上げします。
【心の声】
「正直、うちは目の前の業務に追われていて、それどころじゃない…」
その気持ち、とても分かります。
でもだからこそ、“今”がチャンスです。
忙しい今を変えない限り、未来はもっと忙しく、苦しくなってしまう。
製造業における技術は、“使い捨て”ではありません。
一人ひとりの技術・判断・工夫が、次世代の競争力を形作っていきます。
技術は、道具ではなく“資産”です。
そして、その資産をどう残し、どう使うかは、経営判断そのもの。
“後継者不足”や“現場疲弊”を嘆くのではなく、
「技術を残す仕組み」を持つ企業だけが、未来を選べるのです。
- 「現場のノウハウがベテランの頭の中にしかない」
- 「ツール化やAI導入で記録を自動化したい」
- 「教育や継承の仕組みをつくりたい」
Evoloraでは、現場の知識を“未来の資産”に変えるサポートをしています。
AI・デジタル・改善文化――これらを現場とマネジメントの“橋渡し”として整えます。
まずは、お気軽にご相談ください。
👉【お問い合わせはこちら】
https://evolora.net/contact/
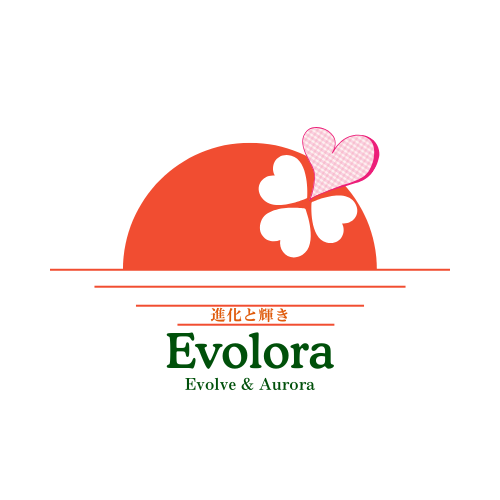 技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー
技術を未来へつなぐ、現場改善のパートナー 


